【授業の「ゴチャゴチャ」に学ぶ】林修先生の話から考える、数学ができるようになる本質
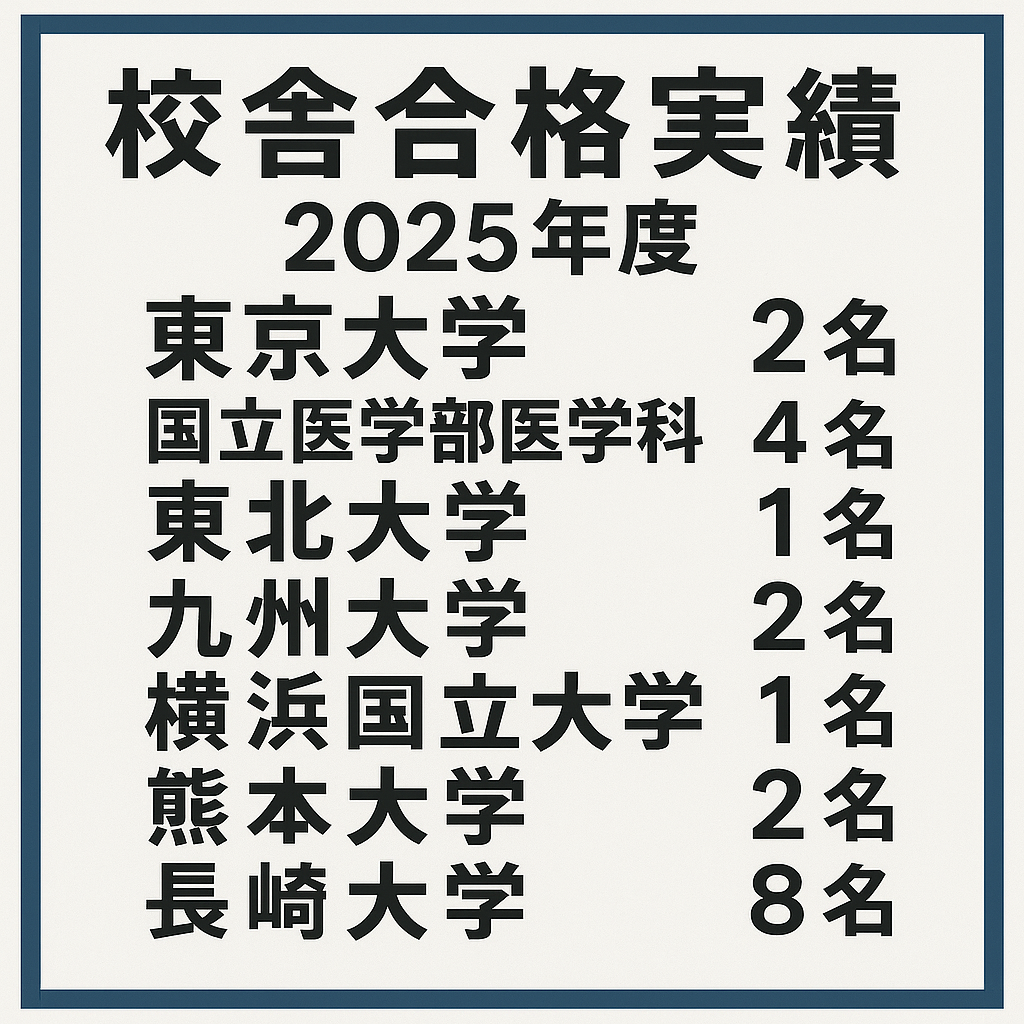

Xの投稿に以下のようなものがありましたので、紹介します。
東進ハイスクールの林修先生が、あるインタビューでこんな話をしていました。
◆ 授業の準備を忘れた「東大数学の回」
林先生がまだ数学の講師だった頃、ある日、授業の直前になって予習をしていないことに気づいたそうです。
その日は「東大の過去問を解説する回」。
いつもは綿密な準備をされる先生ですが、もう時間的に間に合わない。
「今日は休みにしよう」と思い、塾に電話をかけようとした瞬間、
「今一番すべきことは授業に穴をあけないことだ」と思い直し、
ほぼ初見のまま授業に臨んだそうです。
◆ その日の授業の反応
当然ながら、授業中は試行錯誤の連続。
「あーでもない、こーでもない」と考えながら何とか解ききり、授業を終えました。
しかし驚いたことに、生徒たちの反応は意外なものでした。
「ああいう授業が分かりやすかった」
「またやってください!」
林先生は“反省”をしたつもりが、生徒にとっては“神回”になっていたのです。
◆ なぜその授業が刺さったのか
私(山﨑)もこの話を読んで、非常に共感しました。
授業というのは本来、先生がしっかり予習して準備をするのが大前提です。
ただ、この話の本質は「先生や数学ができる人の頭の中の動きが見えた」ことにあります。
数学が苦手な生徒ほど、模範解答のような“完成された式”が
いきなり頭に浮かぶものだと思いがちです。
しかし実際には、そこに至るまでにたくさんの「ゴチャゴチャした試行錯誤」があります。
- 図を描く
- 仮定を立ててみる
- 別の式を立ててみる
- 遠回りをして失敗する
こうした“答案に書かれない部分”こそが、数学の思考のリアルな部分です。
◆ 授業では省かれがちな「過程」
授業では、時間の制約もあり、どうしても綺麗な解答を見せることが中心になります。
でも実際に「考える」とは、遠回りや失敗を含んだプロセスを経験することです。
林先生のその授業は、
「数学ができる人が、実際にどう考えているか」をリアルに見せた授業でした。
生徒が「分かりやすい」と感じたのは、
自分にもできそうだという“現実的な思考の流れ”を感じ取ったからだと思います。
◆ why型思考を持つことの大切さ
私がよく言っている「質問をすることが大事」という話も、
実はこれと同じです。
ただ「この問題の解き方を教えてください(how)」ではなく、
「なぜその考え方になるのか(why)」を質問してみてください。
- なぜこの図を書いたのか
- なぜこの文字を置いたのか
- なぜこの条件を使ったのか
こうした「理由を問う質問」を重ねることで、
思考のプロセスが自分の中に積み重なり、
次に似た問題に出会ったとき、自分で考える力が身につきます。
◆ まとめ
林修先生の“偶然の授業”は、
「模範解答の外側にある思考こそが数学の本質」ということを示してくれました。
授業を受けるとき、
解き方だけでなく「どう考えているのか」に注目してみてください。
質問を通じて“why型思考”を磨くことが、
本当の意味で数学ができるようになる第一歩です。
LINE友だち追加をお願いします!
東進諫早駅前校では、大学受験を目指すお子様向けの情報などを定期的に発信しています。





