【高校生向け】「フィードバック」って何?
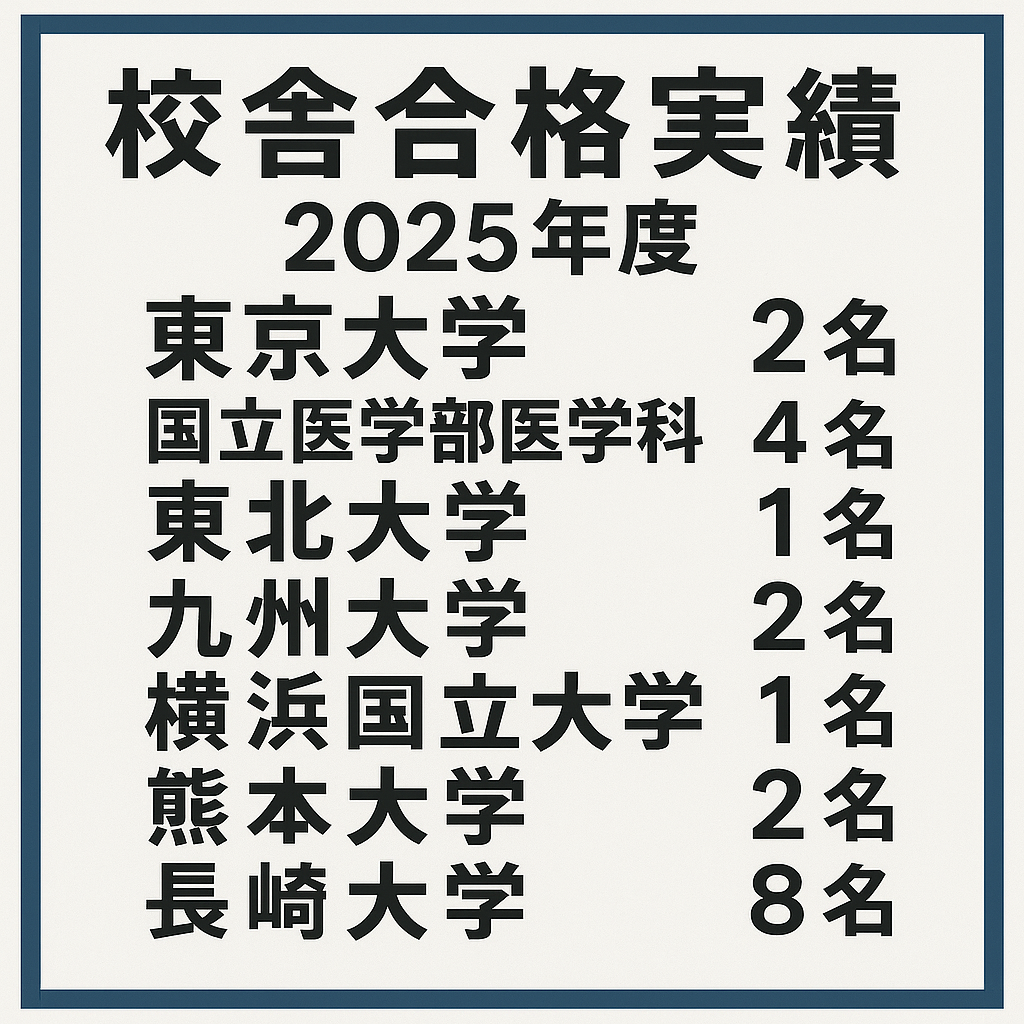

東進の先生が大切にしている“伝え方”と“受け止め方”
――『フィードバック入門』(中原淳)を読んで感じたこと――
最近、東進の先生たちと話していて感じるのは、どの先生も「どう伝えるか」をとても大事にしているということです。
この『増補改訂版 フィードバック入門』(中原淳著)を読んで、その理由がよく分かりました。
◆ フィードバックとは「相手を変える言葉」ではない
本書には、こう書かれています。
フィードバックとは「情報通知」と「立て直し」を通して、相手の成長を支援する育成技術である 。
つまり、「注意する」ことでも「褒める」ことでもなく、**“相手が自分で気づいて変わるためのきっかけを与えること”**が本質なのです。
東進の先生が、ただ「もっと頑張れ」と言うのではなく、
「〇〇の模試で、ケアレスミスが多かったね。どんなときに起こっていたと思う?」
と具体的に聞くのは、まさにこのフィードバックの考え方に近いです。
◆ 経験と人との関わりが成長をつくる
中原先生は、成長には「経験軸」と「ピープル軸」があると述べています 。
- 経験軸:少し背伸びした挑戦(=ストレッチ経験)を通して学ぶ
- ピープル軸:周りの人との関わりから学ぶ
私はここを読んで、「東進の学び方」そのものだと感じました。
講座を受けるだけでなく、**“先生との面談”や“仲間との切磋琢磨”**があるからこそ伸びる。
つまり、経験と人が両方そろって、初めて学びが本物になるのです。
◆ フィードバックは“事前準備”が9割
本書では「フィードバックは準備から始まる」とあります 。
そのときに大切なのが「SBI情報」。
- S(Situation):どんな場面で
- B(Behavior):どんな行動をして
- I(Impact):その結果どうなったか
先生が面談で「模試の結果が下がったね」で終わらせず、「最近は家での勉強時間が減っていたけど、理由は何だった?」と聞くのは、このSBIの考え方そのものです。
**“事実を鏡のように映す”**ことが大切。感情ではなく、行動の事実を一緒に見つめ直す。これが本当のサポートです。
◆ フィードバックを受け取る力も「成長力」
私がこの本を読んで一番感じたのは、「フィードバックは受け取る側の力も問われる」ということです。
耳が痛いことを言われたとき、つい反発したくなりますよね。
でも本書では、こう指摘しています。
人を変えるには「手間暇」をかけ、あの手この手を尽くさなければならない 。
先生たちが本気で言葉をかけてくれるのは、皆さんに変わってほしいからです。
「自分のことを真剣に考えてくれている」と受け止めることが、成長の第一歩になります。
◆ 「褒める」も立派なフィードバック
本書の後半では、ポジティブフィードバックの重要性が強調されています 。
「良いところを見つけて具体的に伝える」ことが、人のやる気を引き出す最強の方法です。
たとえば東進の先生が「最近、毎日登校してるね。継続できるのがすごいよ!」と言うのも、
ただの褒め言葉ではなく、“努力を客観的に見てくれている”というメッセージ。
これが生徒の信頼を生み、次の行動を支えるのです。
◆ まとめ:フィードバックで自分も他人も伸ばそう
この本を読んで改めて感じたのは、東進の先生たちの指導の根底にあるのは「信頼」と「成長支援」だということ。
そして生徒の皆さんには、その言葉を“評価”ではなく“成長のヒント”として受け取ってほしいと思います。
私自身も、先生として生徒に言葉をかけるとき、
「今この言葉は“注意”ではなく、“気づきのきっかけ”になっているか?」
と自問するようになりました。
皆さんも、先生からのアドバイスを“鏡”として自分を見つめ、前に進んでいってください。
✍️ 引用・参考文献
中原淳『増補改訂版 フィードバック入門 部下が成果を出すための最も効果が高い育成の技術』





