【保護者向け】「子どもが本当に思っていること」
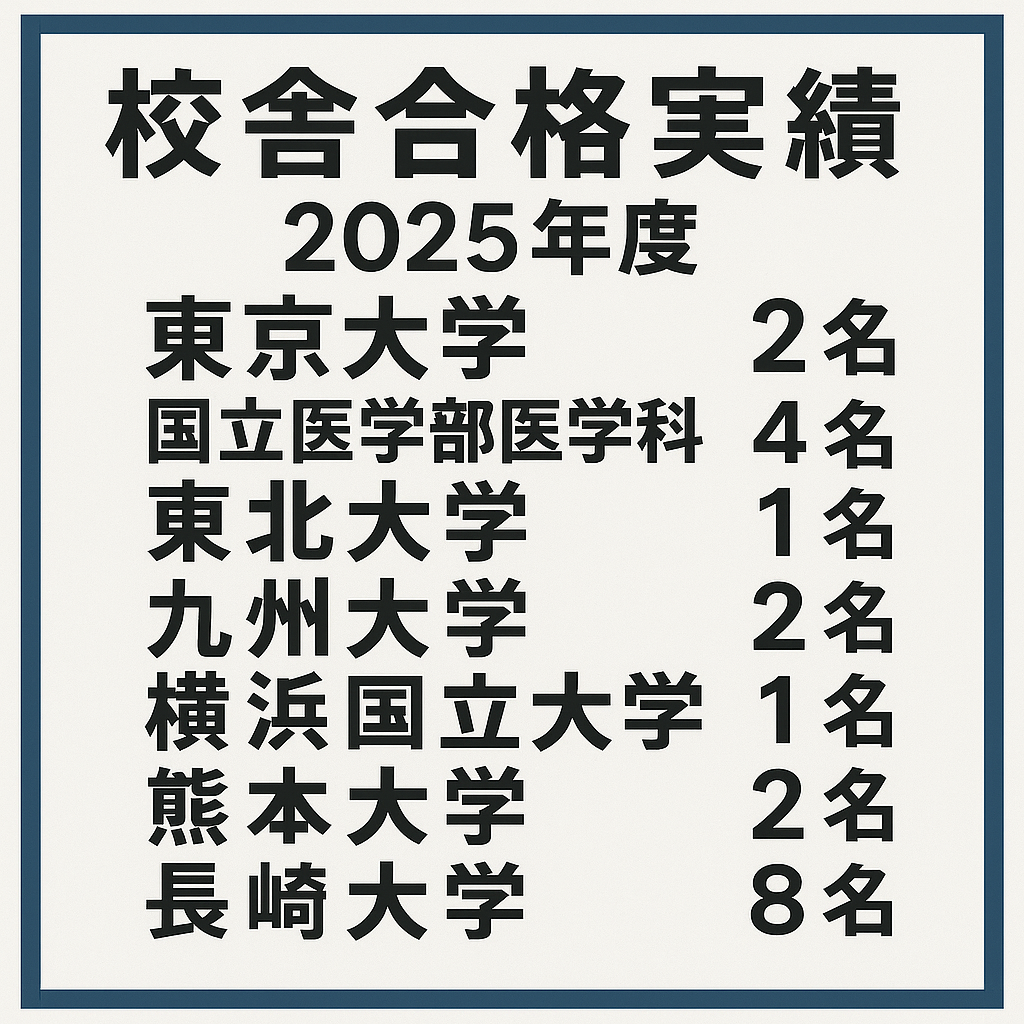

― 子どもを“変える”のではなく、“信じる”ために ―
(『子どもが本当に思っていること』精神科医さわ 著 より)
最近読んだ一冊に、精神科医さわ先生の『子どもが本当に思っていること』があります。
私は教育の現場に長く関わってきましたが、この本を読んで「親の“想い”が子どもにどう届くのか」を改めて考えさせられました。
特に高校生という年代の保護者の方にとって、非常に大切なヒントが詰まっています。
◆ 子どもは「安心したい」だけかもしれない
本書の中で印象に残った一文があります。
子どもの不安をあおるような言葉でコントロールしようとすることは、一時的には効果があるが、長期的には悪影響をもたらしてしまう 。
親として「頑張ってほしい」「失敗してほしくない」という気持ちは当然です。
でも「そんな点数じゃダメでしょ」「もっと努力しなさい」という言葉は、知らず知らずのうちに“安心を奪う”言葉になっているかもしれません。
子どもは失敗を恐れて動けなくなり、「どうせ何をしてもダメだ」と思い込みやすくなります。
だからこそ大切なのは、叱る前に“受け止める”こと。
「よく頑張ってたね」「その方法でうまくいかなかったんだね」と、まず事実を認めてあげる。
そこからようやく、前向きな言葉が届き始めます。
◆ 「お母さん(お父さん)が笑っている」ことの力
さわ先生はこうも述べています。
お母さんが笑顔でいると、子どもは「自分はここにいてもいいんだ」と安心する 。
この部分を読んで、私も思わずうなずきました。
私たちが指導している高校生たちも、どんなにしっかりして見えても、家庭での“表情の空気”には敏感です。
「家に帰るとお母さんがいつも疲れていて、何も言えない」と話す生徒も少なくありません。
家庭が安心できる場所であれば、子どもは挑戦できます。
逆に、家がプレッシャーの場になってしまうと、どんなに意欲があっても伸びにくいのです。
◆ 受験の「結果」をどう捉えるか
受験期の子を持つ親として、誰もが抱える不安があります。
本書では、中学受験の話でしたが、こんな言葉があります。
受験に落ちても親が失敗だと思わなければ、子どもは希望を持つことができる 。
親が「落ちてしまって残念だったね。でも頑張ったことは本物だよ」と言えたら、子どもは次に向かって動けます。
逆に「どうして落ちたの?」と結果を責めてしまうと、その経験は“失敗”に変わってしまう。
私も中学受験や高校受験を指導した経験もありますが、受験指導の現場で、結果に一喜一憂せず「次の一歩をどう踏み出すか」を一緒に考えられる親御さんほど、お子さんの成長が安定していると感じます。
◆ 子どもを信じることは、待つことでもある
著者は「心配性の親ほど、“見ない・待てない・気づかない”傾向がある」と指摘します 。
つい先回りして手を出したくなりますが、それは「あなたには任せられない」というメッセージにもなりかねません。
高校生になると、自分で考え、悩み、失敗する経験そのものが“成長”です。
保護者の方ができるのは、「見守る勇気を持つこと」。
必要なときに、安心して戻ってこられる場所を整えておくことです。
◆ 「あなたがいてくれてうれしい」と伝える
本書の最後に出てくるこの言葉が、私はとても好きです。
子どもがただそこにいてくれるだけで幸せだということ。それを言葉にして伝えよう 。
日本の親は「わざわざ言わなくてもわかるだろう」と思いがちです。
でも、実際に言葉で伝えたとき、子どもの表情がパッと変わることがあります。
たとえ結果が思うようでなくても、「あなたが頑張っている姿を誇りに思う」と伝えること。
その一言が、子どもを支える“心の軸”になります。
◆ おわりに ― 山﨑がこの本を読んで感じたこと
教育の現場では「やる気」「努力」「結果」といった言葉が多く飛び交います。
けれど、子どもの心を育てる根っこは“安心”と“信頼”です。
親が少し肩の力を抜き、「うちの子は大丈夫」と信じてあげること。
その姿勢こそが、どんな学習環境よりも子どもの背中を押すのだと思います。
📘 参考文献
精神科医さわ『子どもが本当に思っていること』




