受験で得られたメリット
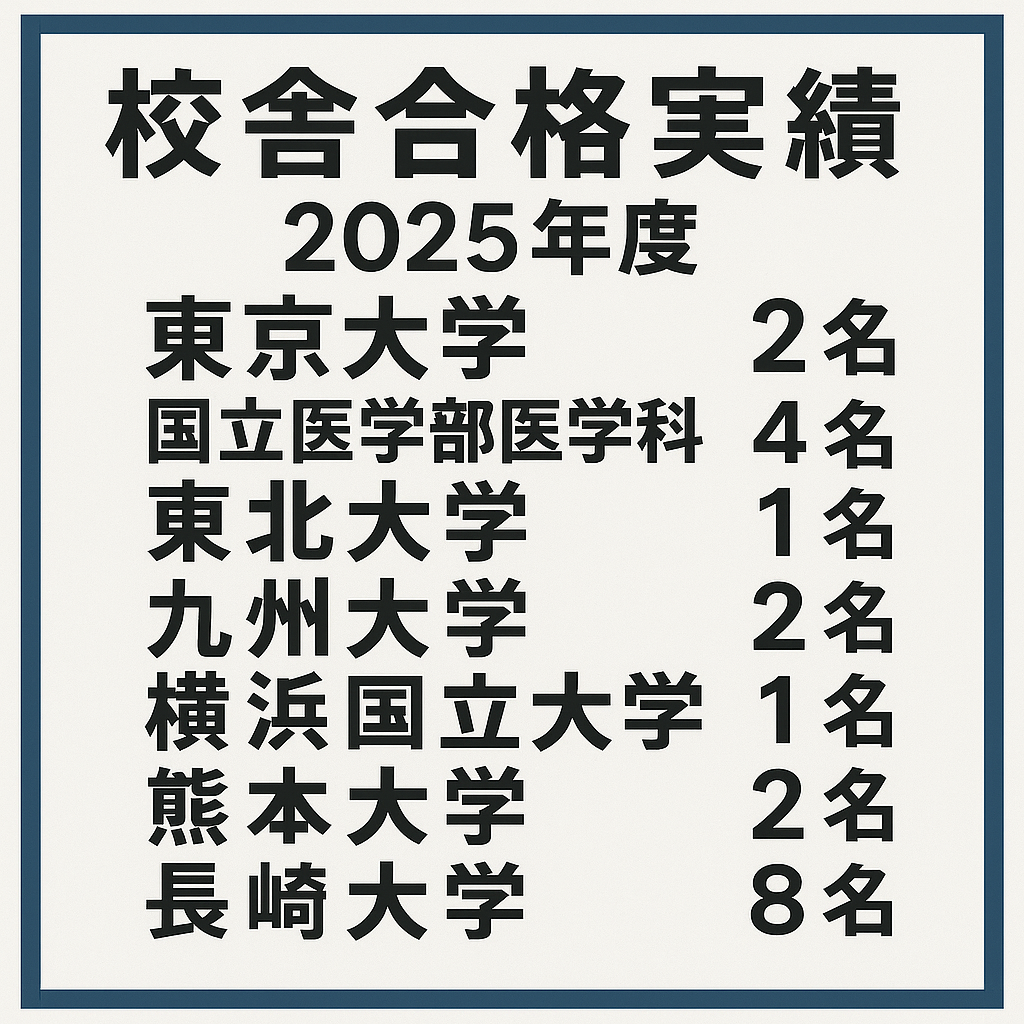

まずは写真を1枚
こんにちは、担任助手の松山です!
みなさん元気でしょうか?学年や環境が変わり大変だと感じていた期間も過ぎ、少しずつ新しい環境に慣れてきた頃でしょう。東進諫早校も新しい先生が加わり新しい環境として動き始め、新体制として本格始動していきますのでみなさんも一緒に頑張っていきましょう!

皆さんお気づきかどうかは分かりませんが、最近は写真を載せるのを怠っていたので今回から再開しようと思います。今回の写真は「瓦そば」です。瓦そばは山口県の定番グルメでアツアツの瓦の上に茶そばを乗せ、卵や肉などを盛りつけた料理で、温かいつゆにつけて食べます。今回の写真は大学の部活で山口に行ったので、その時に食べたものの写真です。皆さんも山口に行く機会があればぜひ食べてみてください。
ブログですが、最近は新しく入った担任助手の先生の挨拶ブログが続いていたので久々書きます。僕は今年で担任助手6年目になり、順当にいけば今年で担任助手を卒業することになります。最後の年だからと言って手を抜いたりするつもりはないのでご安心ください。
受験勉強で得られたメリット
さて、ここからが本題ですが、「大学受験を通して得られたメリット」について、書こうと思います。あくまでも一個人の意見ではありますが参考になると嬉しいです。
重複するものもあるかもしれませんが僕が得られたと思っているものは主に次の3つです。
①限界容量(キャパ)の増加 ➁勉強の仕方 ③タスク管理 あまり長くなっても読む気が失せてくると思うのでここからはできるだけコンパクトに書いていこうと思います。
①限界容量(キャパ)の増加
面談やフロントで話していると、「長時間勉強するのがきつい」という声が聞こえてきます。そんなみんなのモチベにつながったらいいなと思います。僕自身今でこそ長時間勉強することはあまり苦ではありませんが、最初からたくさんのことをやれる体力があったわけではありません。最初から長く勉強をできたわけではないですし、最初の頃はすごくきつかったです。ですが、「きつい中もう少し頑張る」を続けることで、徐々に自分のキャパが増えていき、大丈夫な領域が増えていきました。その結果として、大学のことでもあまり労力を使わずに課題などに取り組むことができているので、よかったと感じています。なので、みなさんもきついと思いながらもほんの少しだけ踏ん張ってみてください。数か月後には勉強体力もついているはずです!
➁勉強の仕方
これについては本当に受験での経験が活きている部分だと思います。大学での勉強でも、まず何をどれだけしないといけないか、どのレベルが必要なのかなどを把握し、取り組むことである程度成果が見えやすく、勉強方針も立てやすくなっているので恩恵を受けているなと感じています。これも、当然最初からできるわけもなく、高校生の頃はすごく苦労しました。試行錯誤・相談を繰り返しながら身に着けていきました。
実際、高校生の頃は東進の先生にもよく相談をしていました。今月から諫早校に来た山崎先生(高校生の頃の諫早校の校長)にもよく相談していました。その甲斐もあり、少しずつどのように考え、勉強していけばいいのかが自分なりに理解でき、その経験が大学でも活用できているので良かったと思っています。
➂タスク管理
受験勉強では多数の科目を平行して勉強し成果を出す必要があります。しかし、すべてをやろうとすると物理的時間が足らなくなってしまうので、優先順位や期限を設けて勉強を進めていく必要があります。そういったことを意識するようにすることで、タスク管理の能力が自然と身についてきます。大学では講義ごとに課題やレポートが課され、提出期限や形式も異なったりするためタスク管理ができると大学に入ってからも非常に役に立つと思います。僕自身タスク管理には現在も苦労する部分もありますが、受験期の経験がなければもっと苦労していたと思います。
最後に
今回簡単ではありますが、僕が思う「受験を通して得られたメリット」について書いてみました。このほかにもたくさん得られるものがあると思いますので、ただ勉強するだけだときついと思うので、少しでも受験を通して多くの事を学び・吸収していってください。もちろん、第一志望校に合格できるようサポートもしていきますが、それ以外の面でもみなさんをサポートしていきますので、一緒に実りのある受験にしていきましょう!
最後に、どの先生でもいいのでどんどん小さなことから大きなことまでどんどん相談するようにしてみるといいと思います!
もし、少し話してみたいな、、と思ってくれた人が居たら話しかけてみてください!
全員いつでもウェルカムなので、ぜひ話しましょう!





